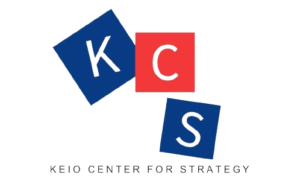カルロ・マサラ著、鈴木理恵訳
『もしロシアがウクライナに勝ったら』(早川書房、2025年)
リサーチ・アシスタント・鈴木文也
ロシアがウクライナに侵攻してから3年以上(クリミア併合からは11年)が経った。開戦当初は地上波のニュースや新聞でもトップニュースになっていたウクライナ戦争は、次第に取り上げられる頻度が減り、扱いも少なくなってきた。どこか遠くの場所で起こっている自分たちには関係ない出来事のようなイメージでウクライナ戦争を見ている人が、日本には多いのではないだろうか。実際に今月(2025年7月)行われる参院選でも、ウクライナ戦争は主要な争点になっていない。ところが、我々が住む日本にとってウクライナ戦争の帰結がもたらす影響は甚大であることを思い起こさせてくれる著作が翻訳出版された。ドイツの著名な国際政治学者であるカルロ・マサラによる『もしロシアがウクライナに勝ったら』である。著者はシナリオ・プランニングという手法で、もしウクライナがロシアに戦争で負けたらという仮定の条件で思考実験を行なっている。それは架空の小説でもなければ、事実のみ書かれているルポルタージュや学術書でもない本書が持つ独創性の一つである。
著者の核心的な主張は、ウクライナ戦争の帰結はヨーロッパにとどまらず、アジアを含む世界各地に波及する可能性があり、グローバルな意味を持つという点にある。なぜなのだろうか。その答えが本書には散りばめられている。本書は、ロシアがウクライナに勝利した後、2028年3月にバルト三国の一つ、エストニアにある小さな町であるナルヴァに侵攻する場面から始まる。ロシアの視野はヨーロッパだけに限定されない。アフリカの親露国であるマリにまで策略の手を伸ばしていく。南シナ海ではロシアに呼応し中国が陽動作戦を実行する。ロシアの攻勢がグローバルに伝播していく様が克明に描かれている。このようなロシアの攻勢を受けてもアメリカや欧州諸国は有効な手を打てない。NATO加盟国とはいえ小さな都市の占領が、第三次世界大戦に繋がることを恐れているためだ。ドイツやイギリスでは正体不明の破壊工作が繰り広げられ動揺が広がる。ロシアの攻勢を受けてもなお欧州のNATO加盟諸国は一枚岩になれない。ロシアの脅威に敏感でない南欧諸国が慎重策を唱える。結局NATOは加盟国であるエストニアの一都市が攻撃されても集団防衛条約である第5条を発動できない。アメリカが発動を拒否したのである。南欧諸国、ハンガリー、スロベニア、極右政権に率いられるフランスまでもがアメリカの主張に賛同する。本書の最後は、ロシアの大統領が中国の習近平に電話をかけるところで終わる。アメリカ主導の国際秩序が終焉を迎え、中国が覇権を握る未来が暗示されている。
本書が提起する論点は多岐にわたる。ロシアによる核の恫喝、NATO集団防衛条約5条の実効性、NATO加盟国間の対露脅威認識の不均衡、欧州の防衛努力の不足などである。しかし、ここでは著者が特に強調する「ウクライナ戦争が持つグローバルな影響」に焦点を当てたい。
著者は日本語版序文で、ロシアがウクライナに勝てば「領土拡張を目的とした武力行使と侵略戦争が二十一世紀の国際政治において常套手段となる可能性」を警告する。とりわけ中国がこの戦争の行方を注視していることは間違いない。アメリカの同盟国へのコミットメントが弱いと見れば、尖閣、台湾への侵攻なども考えられよう。もっとも、この見方には強い反対意見がある。代表的な論者が第二次トランプ政権の政策担当国防次官に任命されたエルブリッジ・コルビーだ。彼は米軍の戦力を中国との有事に備えて集中させるべきだと主張する、対中戦略重視の代表格だ。そのため米国の貴重な軍事支援をウクライナへ提供することへ反対する。あくまでも、アジアで中国を抑止するために限りある軍事力を使うべきだという立場である。
コルビーは村野将氏との対談(村野将『米中戦争を阻止せよ』PHP新書、2025年)で「彼ら(筆者注:権威主義国家)に教訓(筆者注:侵略は誤った決断であるという)を与えておけば、と言う幼稚園児のような議論は止めるべきです。」と言っている(同書、102ページ)。なぜなら中国は現実の軍事バランスを重視しているからだという。つまり、抽象的な理念のためにウクライナに軍事支援をするより、より現実的に、限りある軍事力をアジアに集中させ中国を抑止することに集中すべきだと言う主張だ。
この主張の通り、アメリカや日本はウクライナ支援よりもアジアでの軍事力増強に集中すべきだろうか。第一に考えられる反論は、本書が描くように、ロシアの侵略がウクライナにとどまるとは限らないという点だろう。仮にNATOがウクライナでの戦争に有効に対処できなければ、バルト三国やポーランドへの侵略も現実となる恐れがある。そうなってからでは遅い。欧州諸国が自国の軍事支出を増やし、軍事力を増強し、軍需生産基盤を整えるまで、アメリカはウクライナへの軍事支援を続けるべきであろう。
第二に、ロシアが「核の脅し」によって非核保有国に勝利すると、非核保有国は侵略を恐れて核武装を検討するようになる蓋然性が高まる。あるいは核兵器を用いた恫喝が有効な戦略と認識されることにより、非核保有国が核武装に走る動機が一気に高まる可能性もある。核に対するタブーが強い日本にとっては現実的ではないとしても、韓国やポーランドのような国々では検討の俎上に上る可能性がある。そうなれば核不拡散体制が崩壊し、その余波はサウジアラビアなどにも及ぶだろう。かつてアメリカの国際政治学者のケネス・ウォルツが主張したように「核兵器を持つ国が増えれば増えるほど、核抑止により国際関係が安定する」との主張をとらなければ、予測可能性が失われ、国際関係の安定性は脆いものになるだろう。
また本書の指摘するように明白な侵略行為が行われてもなおNATOの集団防衛条約が発動されない事態になれば、それは日米同盟を抱える日本にとっても他人事ではない。同盟が当てにならないとなれば、自助の原則に従い自国を守るほかなくなる。そのような厳しい状態に耐えられず、自由を犠牲にして中国へのバンドワゴニングを主張する勢力が日本の政界でも出てくる恐れがある。日本がそうなるとドミノ倒しのように、アジアの国々が中国に従って生きるしかない未来がやってくるかもしれない。果たして、そのような未来が望ましいと言えるだろうか。
だが、著者が指摘するように、決してこの本のシナリオは不可避ではない。どうすれば本書のような最悪の帰結を免れるのか。それは、我々がこの戦争を「対岸の火事」ではなく、自らの未来に直結する課題として捉えられるかにかかっている。そうした問いを読者に突きつける本書の意義は極めて大きい。
以上